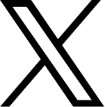お役立ち情報
【今さら聞けない】オフィスレイアウトのコツは?配置や費用も解説
2025.04.11
オフィスで働く社員のモチベーションや生産性を高めるには、レイアウトの工夫が欠かせません。実際にレイアウトを見直すことで、手狭になりがちなスペースを有効活用したり、部門やチームのコミュニケーションを円滑にしたりと、さまざまなメリットが期待できます。本記事では、オフィスレイアウトを最適化するための基本的な考え方から具体的な変更の流れ、費用の相場や改善によるメリットまでをわかりやすく解説します。
目次
オフィスレイアウトを最適化するコツ
オフィスレイアウトを最適化しようと考えるときは、まず全体的なコンセプトづくりから始めることが大切です。レイアウトの方向性が定まると、それに基づいて具体的なゾーニングや動線設計、家具の配置計画を進めることができます。ゾーン分けや動線計画をしっかり検討し、適切な動線を確保することで社員の移動効率が向上し、業務のスムーズな進行やコミュニケーションの活性化につながります。家具や内装を使って快適さと利便性を両立させることも目指します。
レイアウトのコンセプト
オフィスレイアウトのコンセプトづくりでは、自社がどのような働き方を実現したいかを明確にする必要があります。例えば、「コミュニケーション重視」をコンセプトにする場合は、チーム同士が自然と交流できるオープンスペースやコラボレーションエリアを中心に配置し、逆に「集中力の向上」を重視するなら、個別ブースや静音エリアの確保が重要になります。このように適したレイアウトの方向性は大きく変わります。まずは自社の経営方針や人事戦略を踏まえて、オフィスに求める役割を明らかにし、どんなレイアウトなら社員が働きやすいと感じるかを考えてみるとよいでしょう。
レイアウトのゾーニング
オフィスレイアウトのコンセプトが固まったら、次に検討したいのがゾーニングです。ゾーニングとは、オフィスのスペースを機能ごとにわかりやすく区切ることを指します。例えば、来客対応のスペースと社内のスペースを分離しておけば、来客の目を気にせず打ち合わせができるうえに、外部の人に見られては困る情報をうっかり漏らすリスクも減らせます。
レイアウトの動線
オフィスを利用するすべての人がスムーズに動ける動線設計も、レイアウトを最適化するうえで無視できません。動線が悪いと、打ち合わせに向かうだけでストレスを感じたり、同じフロア内を何度も行ったり来たりすることになり、生産性が下がってしまいます。動線は空間づくりの基礎ともいえる要素のため、作業効率と快適性を両立できるよう、実際にその場を歩き回ってシミュレーションを行いながら検討してみるとよいでしょう。
家具や内装
レイアウトのコンセプトやゾーニングが定まったら、それを形にするための家具や内装選びを選びます。オフィス家具は耐久性とデザインの両方が重要になるため、長く使えて社員の満足度も高いものを検討するほうが結果的にはコストパフォーマンスが良いことがあります。照明や床材も含めてトータルでコーディネートすれば、働く環境への満足度がさらに向上する可能性があります。
オフィスレイアウトを変更する流れ
オフィスレイアウトを変更する際は、目的や要件を明確化するところから始まり、プランニングや工事・搬入、そして運用開始後のフィードバックという流れで進めるのが一般的です。一連のステップを踏むことで計画がぶれにくくなり、スムーズにレイアウト変更を完了させられるでしょう。
目的・要件定義
どのような理由でオフィスレイアウトを変更するのかをはっきりさせることは、最初にやるべき重要なプロセスです。例えば、人員増加に伴いデスクを増設する必要があるのか、部署間のコミュニケーションを促進するためにスペースを設置したいのかなどの目標をはっきりさせましょう。また、予算やスケジュールの制約がどの程度なのかを事前に洗い出しておけば、後からイメージと違う結果になったり、コストが想定以上に膨らんだりするリスクを軽減できます。
プランニングと業者選定
目標や要件がはっきりしたら、いよいよ具体的なレイアウトプランを作成する段階に移ります。専門の業者やコンサルタントに依頼してプラン作成をしてもらうと確実です。複数の業者から見積もりやプラン提案してもらい、比較検討することで、費用やデザイン、アフターサポートの質などを総合的に判断しやすくなります。プランニング段階では、家具や内装のイメージをパース図やサンプルを通じてすり合わせることが大切です。
工事・家具搬入
プランが固まったら、実際に工事や家具の搬入を行います。レイアウト変更と同時にネットワークの配線や電源工事が伴う場合も多いため、事前に工程をしっかりと把握しておく必要があります。家具が予定通りに到着するか、工事の進捗に遅れがないかをチェックしながら進めれば、最終的に大幅なロスを防ぎやすくなります。
運用開始後のフィードバック
工事や家具搬入が終わり、新しいレイアウトで社員が働き始めたら、運用開始後のフィードバックを集める段階に入ります。実際に使ってみると、動線の悪さやコミュニケーション上の問題点など、予想外の課題が浮上することは少なくありません。配置を多少見直すだけで解消するケースもあるので、時間を置いてから修正箇所を洗い出す仕組みを作っておくとよいでしょう。
オフィスレイアウトのポイント
オフィスのレイアウトを考えるときには、まず自社の働き方や来客の頻度、そこで働く人々の動線やコミュニケーションの取り方などを総合的に把握することが大切です。外勤が多い社員と内勤が多い社員では、求める設備や理想のレイアウトも異なります。来客対応の多い企業であれば、応接エリアのデザインや場所も重要なポイントになります。ここでは、内勤者が多い場合、外勤者が多い場合、そして来客が多い場合の三つの状況に分けて、オフィスレイアウトを検討するときの考え方をお伝えします。
内勤者が多い場合
内勤者が多い場合では、オフィス内での長時間作業が基本になるため、まずは一人ひとりが落ち着いて仕事に集中できる環境を整えることが大切です。また、ずっと同じ場所で仕事をすると気分転換が難しくなり、集中力が落ちるため、仕事の性質によって席やエリアを変えられるフリーアドレス制を取り入れるのも一つの方法です。
外勤者が多い場合
外勤者が多い場合では、オフィスにいる時間が限られるため、出勤や退勤の際に立ち寄りやすく必要な作業がスムーズに行えるような環境を考えることが重要です。具体的には、外回りの営業や外出から戻ってきた社員が素早く資料作成やメールチェックを行えるように、カウンターやスタンディングデスクなどコンパクトなワークスペースを複数用意することで、すぐに作業に取り掛かることができます
来客が多い場合
来客が多い職場では、まずはスムーズな受付と応対ができるようにレイアウトを組むことが重要です。例えば、エントランスを入ってすぐに受付専用のスペースを設置し、社名やロゴがわかりやすく見えるデザインにするだけでも、初めて訪れる人に安心感や信頼感を与えられます。応接室や会議室はエントランス近くにまとめて配置すると、来客が奥の執務エリアに入り込む必要がなくなるうえ、社員の動線も混乱しづらくなるでしょう。
オフィスのレイアウトのパターン
オフィスレイアウトにはさまざまなパターンがあり、それぞれに特徴があります。自社の働き方や人数、業務内容に合わせて適切なパターンを選ぶことが重要です。代表的なパターンとしては、フリーアドレス式や背面式、同向式、対向式などが挙げられ、それぞれが組織文化や社員の動き方に少なからず影響を与えます。
フリーアドレス式
フリーアドレス式は、個人の固定席を設けずに、社員が自由に席を選ぶスタイルのレイアウトです。出社する人数が流動的な場合や、部門を越えたコミュニケーションを活発にしたい企業に向いています。ただし、どこに誰がいるのか分かりにくいといったデメリットもあるため、チーム内でのコミュニケーションルールやデスク周りの整理ルールをあらかじめ決めておくことが大切です。
背面式
背面式は、その名の通り、お互いに背を向けた状態でデスクを配置するレイアウトを指します。個人作業に集中しやすい一方で、コミュニケーションを促す場面では不便に感じることがあります。オフィスの一部だけ背面式にして、他のエリアでは対話をしやすい配置にするといった使い分けも考えられます。
同向式
同向式は、多くの社員が同じ方向を向いて座るレイアウトです。学校の教室をイメージするとわかりやすいかもしれません。管理職が全体を見渡しやすいという利点がある反面、横のつながりが弱くなりがちで、部署間の連携に物足りなさを感じることもあります。背面式よりはコミュニケーションを図りやすい場合が多いので、一斉に連絡事項を伝えたいような業種にも向いているかもしれません。
対向式
対向式は、社員同士が向かい合って座る配置です。顔を合わせやすい分、会話がしやすくなるというメリットがありますが、人によっては常に視線を感じるために落ち着かないと感じることもあるでしょう。間にパーティションを設けたり、テーブルのレイアウトに変化をつけたりすることで、コミュニケーションのしやすさと個人のプライバシーを両立させるアイデアも生まれます。
オフィスレイアウトを最適化するメリット
オフィスレイアウトを最適化することは、新しいデスクを導入するといった単なる設備更新ではなく、働く環境を見直す重要な取り組みです。よく練られたレイアウトは、社員の気持ちと体を軽くし、自然と生産性やコミュニケーションの質が向上する効果をもたらします。
手狭感の解消
限られたスペースに無理やり席を詰め込んでしまうと、動きづらさを感じるだけでなく、集中力やモチベーションの低下につながります。レイアウトを最適化することで、同じ面積のオフィスでもゆとりを感じさせる配置が可能になり、手狭感が大幅に解消できる可能性があります。十分な通路幅や余計な家具を減らす工夫を取り入れれば、疲れにくく快適に働ける環境を作ることができます。
組織変更への対応
企業は人事異動や新規事業の立ち上げなど、変化がつきものです。そのため、オフィスレイアウトが硬直的だと、組織が変わるたびに大規模なレイアウト変更が必要となり、手間もコストもかさんでしまいます。最初にしっかりとゾーニングや動線を設計しておけば、組織の変化に合わせたマイナーチェンジで済み、大がかりな再工事をさけることができるメリットがあります。
オフィスレイアウト変更のコツを知って最適化しよう
オフィスレイアウトは単にデスクを並べるだけでなく、企業がどのような働き方を目指し、社員がどんな環境で力を発揮するかを具現化する重要な要素です。レイアウトが変わることで、自然と社員同士の距離感やコミュニケーションの在り方も変化し、それが企業の文化に影響を及ぼす可能性もあります。オフィスは社員が長く過ごす場所であるという意識を持ち、ぜひ自社にとって理想的なレイアウトを検討し、実現してみてください。
つながるオフィスでは、オフィスの仲介から内装・設計まで一貫して手がけておりますので、企業のニーズにぴったり合ったオフィスのレイアウトをご提案可能です。オフィス移転やレイアウト変更をお考えの際は、ぜひご相談ください。
CONTACT US CONTACT US
居抜きオフィス物件の
入居・募集なら
つながるオフィスへお任せください

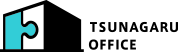
 居抜き物件を探す
居抜き物件を探す お問い合わせ
お問い合わせ つながるオフィスについて
つながるオフィスについて
 居抜き物件を登録(無料)
居抜き物件を登録(無料)
 サステナビリティ
サステナビリティ
 よくある質問
よくある質問
 お役立ち情報
お役立ち情報
 お知らせ
お知らせ
 はじめての方
はじめての方
 閲覧履歴
閲覧履歴
 お気に入り
お気に入り